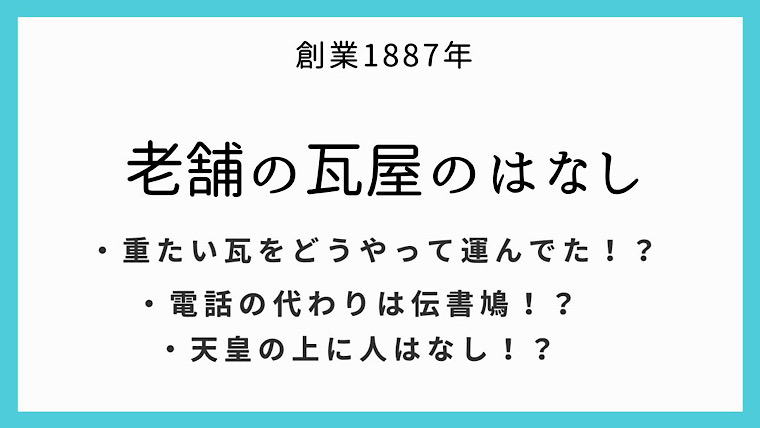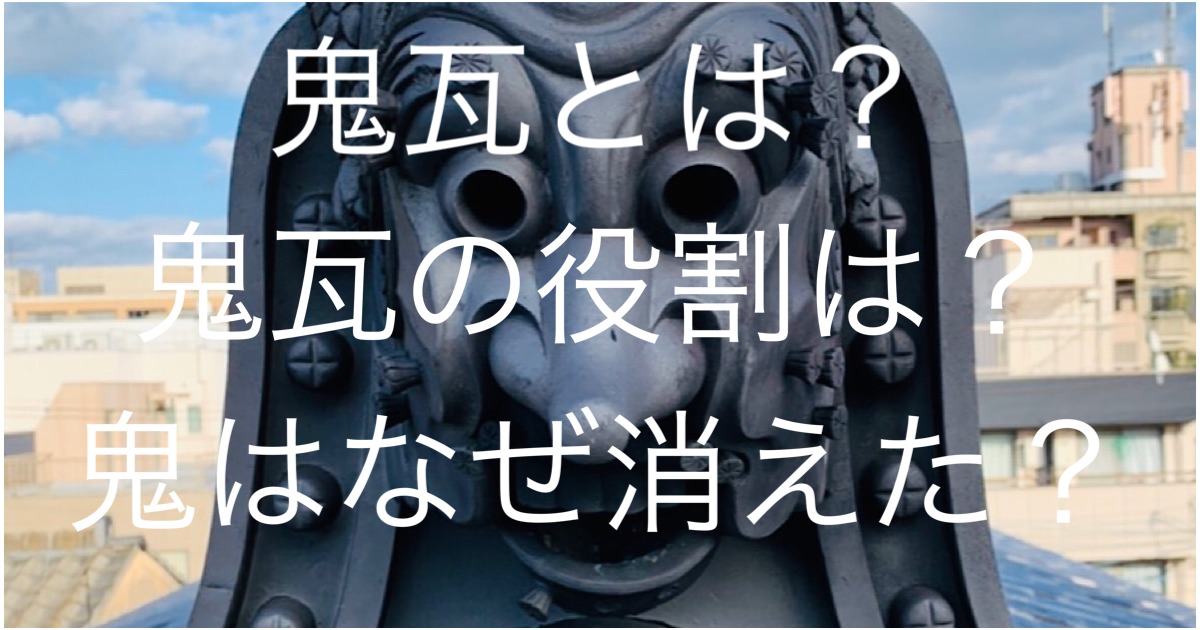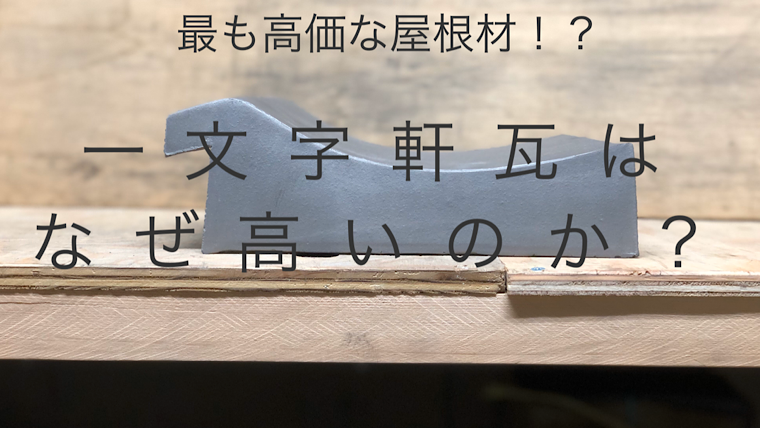おかげさまで弊店は今年で142年を迎えました!(^ ^)
今回は、その歴史の中で、我が家に伝わる昔話をご紹介いたします!
重たい瓦をどのように運んだか
現代では瓦を運ぶ際、軽トラックやダンプカーなどを利用しますが、車がない時代、昔の職人たちはどのようにして重たい瓦を運んだのでしょうか?
祖母から聞いた話では、大八車というものを利用し、2人1組で運んだそうです。
大八車に山ほど瓦を積み、運ぶだけで一日の仕事が終わるのは当たり前の話でした。

大八車
*Wikipediaより
電話の代わりに伝書鳩
昔の事業所の写真を見てみると、大屋根部分に鳩小屋が建てられていたのを見つけました。最初はただ鳩を飼っていたんだろうと思いましたが、伝書鳩として飼育されていたものだと教えられました。
昔話で出てくるような話ですが、明治時代では軍事用にたくさん輸入され、民間でも飼育されていたそうです。
現代でこそ自動車などの普及で容易に移動が可能ですが、百年ほど前ではそうはいきません。移動するだけでも大仕事になります。
また、携帯電話なども発明されていなかったため、地方の出張の時などは特に困難でした。瓦が足りなくなったり、必要な道具が増えたりした場合には、何十キロ離れた場所まで現場の職人が戻る必要がありました。
そこで先々代が何十羽という鳩を飼い、現場まで持って行き、屋根を見て「あの瓦が何枚、この瓦が何枚」と書いたメモを鳩の脚にくくりつけ、一気に放ったそうです。
何十羽と持っていくのは、途中で逃げたり、天敵に襲われたりと、帰ってこないことを見越してのことです。中には血だらけで帰ってくる鳩もいました。
そして命からがら帰ってきた鳩からメモを受け取り、事業所に待機している後発の職人が瓦を積んで現場まで持って行ったそうです。
この方法により、1往復で仕事が済むようになりました。
鳩には可哀想な話ですが、電話も無い時代、これが最善の方法だったようです、、、🕊
天皇の上に人はなし
現在の事業所に移る前、弊店は京都御所の堺町御門前に店を構えていました。
明治時代、天皇陛下がまだ京都にお住まいの頃、先々代が御所の屋根を工事させていただくことになったそうです。
現場に着くと、関係者の方に白い着物を渡され、「これを着て仕事をして欲しい」と言われました。
のちに聞いた話では、陛下が屋根に上がる白装束の職人を見て、「あれはなんじゃ?」と聞かれ、側近の方が「あれはただの鳥でございます」と答えました。
やはり陛下の頭の上に上がるのは無礼になるらしく、鳥ならば仕方ないということになったそうです。
いかがでしたでしょうか!
毒にも薬にもならない話でしたが、最後まで見ていただければ幸いです。
それでは、また次の記事でお会いしましょう!
ありがとうございました!!!(^_^)